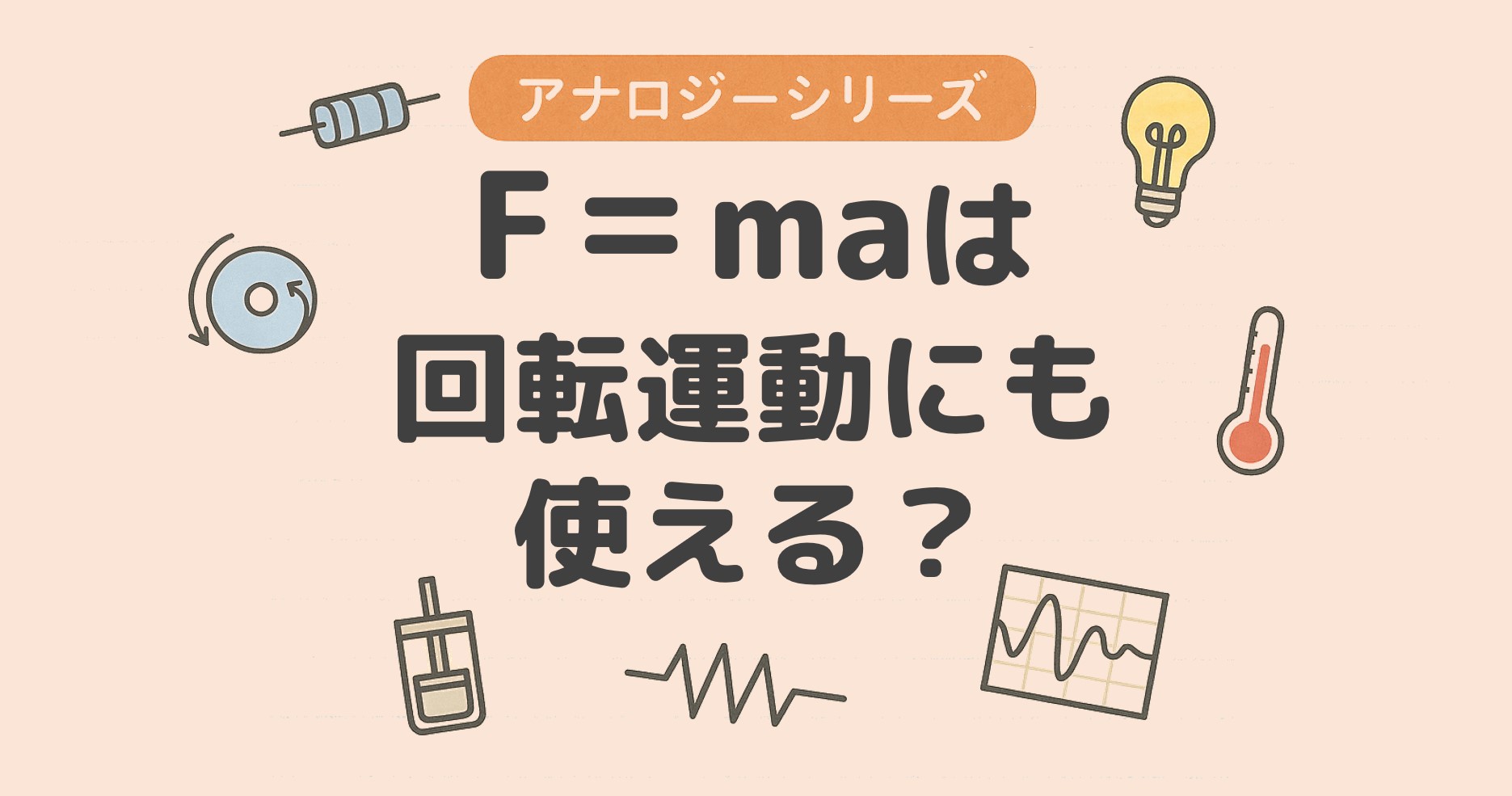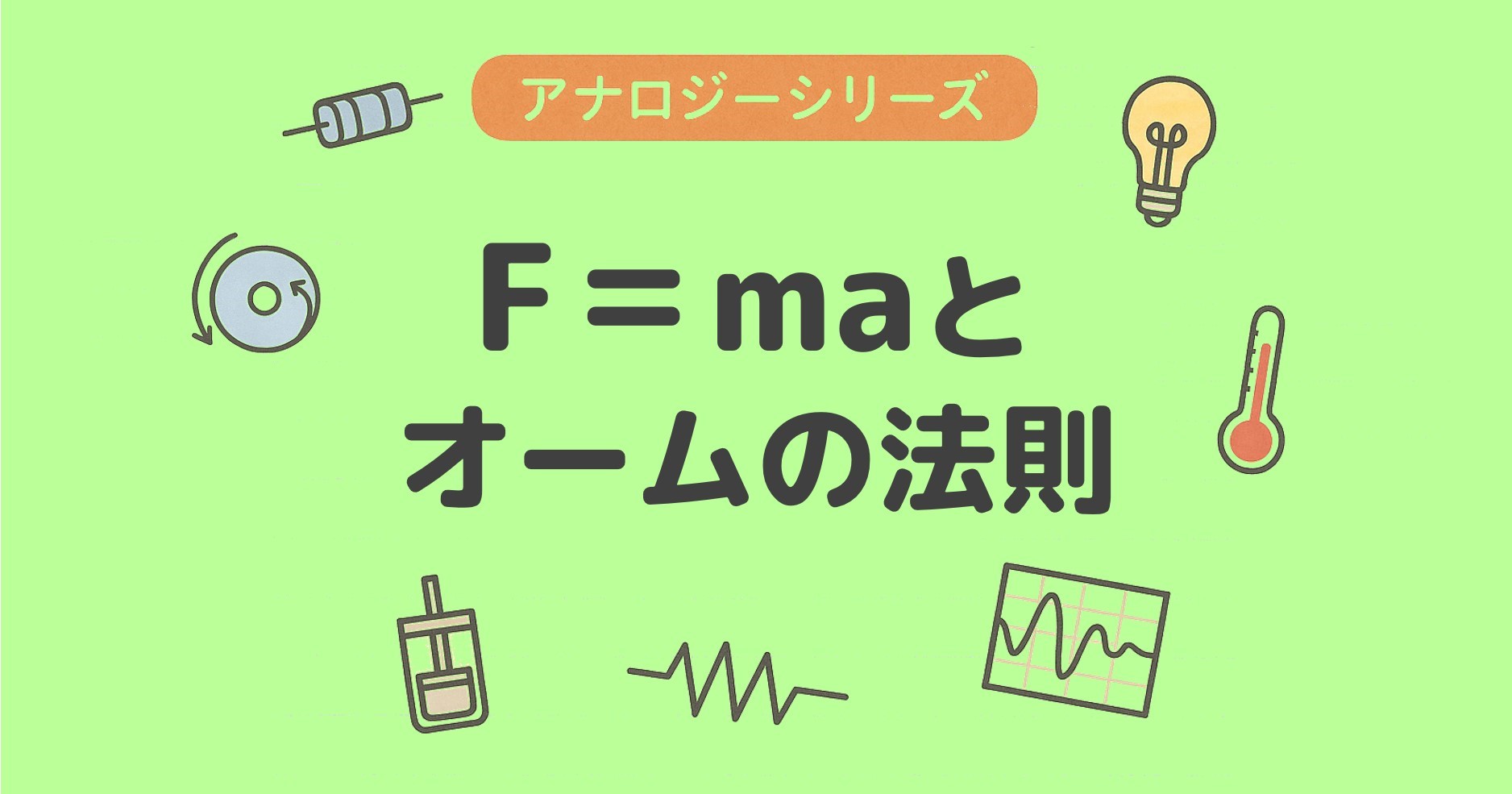はじめに
最近、AIや自動化技術の進歩が目覚ましく、「人間が働かなくても生きていける未来」が現実味を帯びてきました。だけど、それって本当に実現するの?
そして、もし実現できるなら、何がその障壁で、どこから手をつければいいのか?
この記事では、「本当は家でゲームしてのんびり暮らしたい。でも、その未来を真面目に考えてる」僕の視点から、社会全体で”楽に生きる未来”を実現するための条件を整理してみます。
僕の立場:作る人間
まず前提として、僕は「作る側の人間」です。AIや自動化技術を活用しながら、製造業の現場で効率化や品質向上に取り組んでいます。でも、正直に言うと――
本当は家でゲームして暮らしたい!
だからこそ、「どうすればそれが可能な社会になるのか?」を真面目に考えてみました。
まず考えるべき4つの壁
- 社会構造の壁
- 哲学的な壁(人間の価値観)
- 経済モデルの壁
- 技術課題の壁
これらがクリアできたとき、ようやく「楽に生きられる未来」が現実になります。それぞれ見ていきましょう。
社会構造の壁
ここで言う”社会構造の壁”とは、法律・制度・雇用システム・教育・税制など、社会全体が前提としている枠組みのことを指します。
例:
- 働かない人への社会的まなざし(ニートへの偏見)
- 年功序列や終身雇用を前提とした働き方
- 勉強→就職→定年という一方向の人生モデル
ただ、これは最近少しずつ動き出している気がします。
- 政治に関心を持つ人が増えてきた
- WebメディアやSNSによって情報が民主化されてきた
- 若い世代が「ルールそのものを変える」ことを志向し始めた
つまり、時間がかかってもここは自然に変わっていく部分だと思っています。
哲学的な壁(人間の価値観)
「人は働かずに本当に幸福か?」という問い。
これはかつてのマウス実験(通称:ユニバース25=ネズミの楽園実験)でも議論されました。環境を整えても、目的のない生活では崩壊する。
でも、人間はネズミと違います。
- 承認欲求がある
- 達成感を求める
- 「楽しい」を他人と共有できる
たとえば、Youtuber、音楽活動、創作活動――
“みんなで楽しいを作る” という営みは人類からなくならない。
だからこの壁は、小さな成功例(ミニモデル)を積み重ねれば超えられると信じています。
経済モデルの壁
ベーシックインカム(BI)を実現できるか?
これは上記2つ――社会構造と価値観の変化――が実現すれば、おのずと見えてくる壁です。
なお、制度だけを先に整えようとしてうまくいかなかった例もあります。たとえばフィンランドでは、2017年〜2018年にかけて2000人を対象にしたベーシックインカムの実証実験が行われましたが、「雇用改善や幸福度向上には大きな成果がなかった」とされ、制度化には至りませんでした。
つまり、制度先行では失敗する可能性が高く、社会や価値観の下支えが不可欠ということです。
- 働かなくても最低限暮らせる社会
- そこに”遊び”や”創造”で稼げる選択肢が加わる
これができたとき、”楽する”が初めて制度として認められます。
技術課題の壁(ここが最も重たい)
製造業にいると、ここが一番リアルに大きな壁に感じます。
- ロボットは劣化する
- 保守メンテが必要(人手がかかる)
- 良品率が不安定だと自動化の意味が薄れる
もし「100年劣化しない素材」や「自己修復するロボット」ができたら一気に世界は変わります。
でも現状はまだ遠い。
だから僕たちは、ここに知恵とエネルギーを注ぐ必要があると感じています。
まとめ:楽する未来は、僕たちが”投資”しないとやってこない
- 僕たちは、”楽をする”ためにこそ、今がんばる必要がある
- AIでルーチンは減らせても、”やりたい”を叶えるには人間の力が必要
- 社会全体が整うには時間がかかる。でも、整える人が必要
今はまだ遠い未来かもしれない。
でも、「家でゲームしながら気ままに生きる」未来を目指して、今日も現場で汗をかきながら、技術を積み上げています。
それって、けっこう悪くない未来への投資じゃないですか?